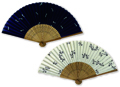夏のイベントには、うちわ!
夏になれば、どこかで必ず一度は手にするうちわ。そんなうちわも今では様変わりしています。
よく目にするうちわは、ポリうちわと言われるものになり、これが今でも一番人気のうちわとなっています。
その次に多いのが、ペーパーファンと言われる紙で出来たうちわです。
その他には、フォールディングファンという折り畳んで持ち運びがしやすいうちわも開発されています。
うちわの扇ぎ方
うちわを扇ぐ方法として力任せに扇ぐ方法が多いかと思います。これは刑事ドラマでのシーンや酢飯を冷ます時の扇ぎ方やバーベキューで火を起こす際に使う方法などがイメージされるからです。しかし、力任せに扇げばエネルギーを使う事になりますので、
続きはこちらから
うちわが涼しい理由
これは人工的に風を起こすことにより自分の体に風を送る事で涼しさを感じます。実際、秒速1メートルの風を受けると体感的に体感温度が1度下がると言われています。たしかに、気温が高くても強風の日などはとても寒く感じます。
続きはこちらから
うちわの活用
夏の風物詩うちわですが、日本の夏になくてはならない貰って嬉しい販促品です。屋外でのイベントなど、猛暑の日に貰えると満面の笑顔になります。
続きはこちらから
「うちわ」の大きさ
レギュラーサイズが3種類の中で一番大きなうちわです。全体のサイズで天地が345mm
幅が243mmあります。一番使いやすいサイズです
。
続きはこちらから
ペーパーファンにつき
うちわの中でも一番安価に作成できるのがペーパーファンです。機基本的に厚紙を丸く抜いたうちわですので非常に安価で作成できます。大きさは大体20センチ程度が主流になります。
続きはこちらから
フォールディングファン
うちわには様々な種類がありますが、非常にコンパクトかつ丈夫なうちわがあります。名前は「フォールディングファン」です。持ち手はプラスチック製で、うちわ部分も化学繊維で出来ているので非常に強度もあります。
続きはこちらから
紙エコうちわ
うちわには様々な種類のうちわがありますが、エコブームの中誕生したのが紙エコうちわです。形状は殆どポリうちわと同じですが、全てのパーツが紙で出来ています。持ち手の部分もポリに負けない強度もあり、
続きはこちらから
まんまる小型うちわ
うちわの種類の中で、まんまる形状のうちわがあります。品名は「まんまる小型うちわ」です。うちわの部分がまんまるなので、丸い商品等の宣伝に非常に有効です。
続きはこちらから
3連丸うちわ
完成形はペーパーファンと同じ丸うちわですが、圧着ハガキのように横に3枚繋がっていて広げると表3枚裏3枚の面積があり、通常のペーパーファンの3倍の広告内容を印刷する事が出来ます。
続きはこちらから
うちわの年間作成数
うちわの製作本数は約9200万本作成されています。その約9割は四国の丸亀で作らています。
現在のうちわはほぼ骨がポリで作られたうちわになっています。昭和30年頃は全てが竹うちわで、約9000万本作られていました。
続きはこちらから
うちわの歴史
平成9年5月、丸亀うちわは国の伝統的工芸品に指定されています。
風情あふれる丸亀うちわは、夏に欠かせない風物詩として多くの人に愛されています。
続きはこちらから
変わり種うちわ(グルグルうちわ)
うちわにも種類があり、通常のプラスティック素材のうちわや昔ながらの竹でできたうちわもあります。
今回紹介するのは画像の中心の太い棒を持ってグルグル回るうちわです。今までに無い変わったうちわです。
続きはこちらから
「うちわ」作成工程
うちわには様々な種類がありますが、定番のポリうちわの作成は下記の工程があります。1.骨の部分を作成・・小さな丸状のポリ材料を機械に入れ込み、この材料が解けて骨の型に流し込まれます。
続きはこちらから
扇子の想い出
私がまだ独身で若いころ、父親から一本の扇子をもらいました。上品なしっかりしたもので外から見たら百貨店で買ってきたのかと思うようなものでした。広げてみると骨の内側にさりげなく
続きはこちらから
巨大うちわ
うちわの中でも、イベントやお祭りで使用するうちわで、巨大なうちわがあります。
あまり見かける事がないですが、限定品で製造する事が出来ます。
続きはこちらから
京うちわ
京うちわの歴史は古く、元禄2年(1689年)にさかのぼります。京都のうちわ文化は阿以波が代表的なうちわです。阿以波は初代長兵衛が近江の国から都に出て店をひらいて始まっています。
続きはこちらから
「うちわ」ポスティング
近年温暖化の影響を受け、非常に暑い日が増えてきています。販促商品は様々なアイテムがありますが、初夏から8月に向けて一番人気の商品と言えば「うちわ」になります。イベントでの配布も多いですが、街頭でのポスティングにも多く活用されるようになりました。
続きはこちらから
紙扇子
最近扇子の人気も高まり、折りたためる事が出来るので非常にコンパクトになり持ち運びが簡単です。一般的な扇子は竹を使用しますが、全ての材料を紙で作成できるエコな扇子になります。
続きはこちらから
雪村うちわ
う茨城県に古くから伝わるうちわがあります。雪村うちわです。 室町時代、水彩画家の雪村が作り始めたうちわになります。竹で作った骨に西ノ内和紙を使って骨に貼り付け、馬や景色等の水墨画が書かれたうちわになります。
続きはこちらから
越生うちわ
日本全国には様々な地方特有のうちわが存在しています。埼玉県越生町(おごせまち)に伝わる「越生うちわ」があります。このうちわは最盛期の明治時代には約240万本も作成されていました。
続きはこちらから
房州うちわ
千葉県房総半島の南部を明治時代に「安房国」と呼ばれていました。その一文字を取って「房州」の名称が生まれています。最近では房総と同じ意味合いで「房州」とも言っています。
続きはこちらから
佐渡うちわ
新潟県には以前真野という地域がありました。この地域に古くから竹を使ってうちわを制作する職人がいました。真野の地域で作るうつわを真野うちわと呼んでいました。真野うちわには佐渡伝統芸能の熊の絵柄やのろま人形などの絵柄が多く使われていて多くの方に広く親しまれています。
続きはこちらから
表面加工につき(うちわ)
ポリうちわを作成する場合、紙に図柄を印刷しますが、その上にニスを印刷します。これは光沢が出る効果もありますが、印刷しましたインキが服等につかない効果もあります。ベタ印刷等の場合、強くこするとインキが手についたりします。
続きはこちらから
名古屋扇子
今日本の伝統工芸品の多くは元々中国がルーツとする物が多いですが、この扇子は日本で生まれたオリジナルの扇子になります。
ルーツは平安時代初期にさかのぼりますが、
続きはこちらから